広兼邸とは?
岡山県高梁市成羽町の吹屋の町並みから南方約3kmにある、 笹畝坑道 や ベンガラ館・吹屋小学校 などとともに 吹屋ふるさと村 を構成する観光スポットの1つで、1985年2月に広兼家より岡山県へ寄付された邸宅。
江戸時代後期の享和・文化年間に、小泉銅山の経営と吹屋の代名詞でもあるベンガラの原料となるローハ製造により巨万の富を得た広兼家の邸宅で、庄屋でありながら豪商ぶりを見せた2代目当主 元治が1810年に築造。
約780坪もの敷地には、約98坪の本宅、約35坪の離れ座敷、約31坪の長屋、約46坪の土蔵など全56部屋があり、映画『八つ墓村』『燃えよ剣』のロケ地としても知られる。
1984年に旧成羽町、現在の高梁市の重要文化財となると、2020年6月19日には「旧広兼家住宅」として日本遺産 "「ジャパンレッド」発祥の地" の構成文化財に指定されている。
広兼邸 の 広告
城郭のような邸宅をご覧あれ!
高石垣と見張りまでいた楼門造りの門構えに注目! 駐車場から庄屋屋敷とは思えない圧倒的な威圧感をしばし堪能しよう!
随所に見られるベンガラ色に注目!
個人宅では考えられない部屋の数々と、随所に見られる本場のベンガラ色に注目!
映画『八つ墓村』と『燃えよ剣』のロケ地だよ!
日本遺産「旧広兼家住宅」は映画のロケ地としても有名だよ! あのシーンがココで…。
広兼邸 の 魅力
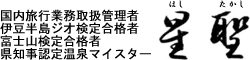


広兼邸 の 見どころ

広兼邸
実に荘厳な眺めだ! 観光地化された今でも近づくのがはばかれるほどの圧倒的な威圧感だ。この写真は駐車場から撮影したのだが、車を降りこの光景を目の当たりにした時には、まるで難攻不落の敵の城に犬死にしに行くかのような面持ちとなった。清正もビックリの武者返しのような高石垣は、これで半分は土に覆われているというから驚く。中央の楼門には24時間体制で門番がつめていたというから、この距離この角度で見下ろされたら身動きも出来ない。庄屋と言えども、いかに事業で成功を収め財を成したかが、如実にこの石垣と門構えに表れている。

駐車場からのアプローチ
とにかく自然豊かで眺めの良い所で、写真左手方向に広兼邸があり、駐車場からはその遺功を眺めつつ、ぐるりと回り込みながら坂を上って行くのだが、驚くのは写真右手方向の尾根に建つ「天広神社」だ。広兼邸と対峙するように個人の神社として建てられたもので、天広の"広"は言うまでも無い。

銅と弁柄の里 吹屋 広兼邸
19世紀初頭の江戸時代に2代目当主 広兼元治がローハ製造で財を成し築いた庄屋屋敷なのだが、20世紀となり三菱系だった広兼家当主が東京へと引越し、留守居が2代に渡って家を守ってきたのだが、1984年に旧成羽町の重要文化財に指定されると翌1985年2月に広兼家より岡山県へと寄付された。

映画『八つ墓村』&『燃えよ剣』のロケ地
「祟りじゃ~っ!」のセリフで知られる、横溝正史原作の映画『八つ墓村』のロケ地となっており、萩原健一さん主演で渥美清さんが金田一役だった1977年版と、豊川悦司さん主演の1996年版の2度行われている。更に2021年公開の岡田准一さん主演の映画『燃えよ剣』の断髪シーンも広兼邸でのロケ!

日本遺産 旧広兼家住宅
近づくにつれその屋敷の凄さをまざまざと感じる。地元静岡の国指定重要文化財の大鐘家あたりをイメージして訪れたのだが、その比ではなかった。外観やアプローチが似ているあの柳生の里の柳生藩家老屋敷をも凌ぐ感じだ。2020年に"旧広兼家住宅"として日本遺産の構成文化財に指定されている。

広兼邸の楼門
これが江戸時代の1810年に造られた楼門だ。外観とは裏腹に敷地内からは高低差により1階部分が半地下のように隠れて見えることもあり、威圧感はそれほど無い。2階が不寝番部屋となっており、ここから24時間体制で見張りが行われていた。くどいようだが、城でも武家屋敷でもないのにだ!

天守閣のような格子越しの眺め
冒頭に「中央の楼門には24時間体制で門番がつめていたというから、この距離この角度で見下ろされたら身動きも出来ない。」と書いたが、ご覧のとおりだ。山を上ってくる者や、近づく人の動きが手に取るようにわかる。この格子越しの眺めは、まるで天守閣のようだ。

広兼邸の主屋(本宅)
広兼邸の本宅となる、1810年に建築された97.7坪の主屋だ。入母屋には家紋入りの鬼瓦、菱形の大きな換気口、帯状に巡らされた漆喰による文様があり、下屋にも別の文様が巡らされていて、ただならぬ家だという印象を漂わせている。

客間→玄関→店の間→控え間
本宅の和室の続き間。手前から客間→玄関→店の間→控え間と続き、一番奥に台所が見える。右手に主人の居室や寝室・居間がある。襖絵にわずかに金箔が見られるものの生活空間らしく落ち着いた雰囲気…と思いきや、欄間装飾は凄い!

水琴窟
客間の前の樹木の裏手に、日本庭園の美の結晶である水琴窟がある。竹が刺さっており、耳を近づけると、日本人の心の琴線に触れる透き通った美しい音色が聴こえる。

台所
かまどの数もさすがといった感じの台所なのだが、驚いたのが漬け物専用の置場や精米場があり、さらには料理場は奥の部屋で別だということだ。台所で調理はしないんですね…。

水汲み場
広兼邸の背後の裏山から湧き出る清水を貯めておく、本宅の端に設けられた水汲み場だ。すぐ裏が崖となっている立地をうまく活用した感じで、井戸ではなくこの水を生活水として利用していたようだ。今も石の間より水が湧き出ており、小さな祠の周りが濡れている。

使用人の浴室
使用人の浴室ということで、無造作に五右衛門風呂がただ置かれているのかと思いきや、美しいタイル張りの部屋の隅に、しっかりとした造りで固定されている。しかも跨いで入りやすいように段まで付けられている。これで使用人の浴室というから驚きだ。

みそ蔵・土蔵
本宅の裏手に回ると見られるのが、このみそ蔵&土蔵である。でっかく広兼家の"外雪輪に剣片喰"の家紋が入り、漆喰鏝絵やなまこ壁などの造りも凄い。みそ蔵にも驚くが、土蔵にはどんな財宝が眠っていたのか…。

離れ座敷
本宅よりも後の大正時代に造られた、35.4坪の美しい佇まいを見せる離れ座敷。本宅に対し格子欄間など縦のラインが印象的だ。驚いたのは、この離れ座敷は当主の結婚式で一度しか使用されていないということだ。

もはや個人宅ではない‼
床の間や違い棚がある離れ座敷。屏風や衝立障子などの調度品にも驚いたが、畳の敷き方がもはや個人宅ではない。寺院や武家屋敷の大広間のように、目が十字になる不祝儀敷き(四ツ井敷き)となっている。廊下を隔てて奥に浴室が、2階に隠居部屋がある。

離れ座敷と土蔵
手前が茶室もある離れ座敷で、奥に見えるのが主に米蔵として利用された土蔵だ。写真には写っていないが、その奥に乗馬用の厩と道具などを置く土蔵がある。ここでもローハ製造で財を成した家らしい佇まいが見てとれる。塩田瓦も印象的だ。

長屋
楼門の左手となる南西方向に、主屋と同じ1810年に建てられた31.2坪の長屋がある。手前に下男部屋と番頭部屋があり、厩肥落しを隔てて下女部屋がある。その奥に厩や種こんにゃく保存室、厠があり、仔牛小屋と農作業場が続いている。下女と女中は明確に異なり、女中部屋は本宅の2階にある。

個人宅ではありえない部屋!?
楼門があること自体凄いのだが、そこの2階にある文字通り寝ないで24時間体制で見張りをする不寝番部屋。そしてその門番たちの部屋。奥の小窓は門に通じている。さらに本宅にある漬物専用の置場や精米場など、広兼邸には今じゃ考えられない部屋がある。
広兼邸 の 見頃・おすすめ時期
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
広兼邸 の 基本情報
| 名称 | 広兼邸 |
|---|---|
| 読み方 | ひろかねてい |
| 英訳 | Hirokane-Tei Hirokane Residence |
| 郵便番号 | 〒719-2342 |
| 所在地 | 岡山県 高梁市 羽町中野2710 |
| 駐車場 | あり |
| お問合せ | 0866-29-3182 |
| アクセス | 現在地 からの ルート と 所要時間 |
| 登録・指定 | 日本遺産 高梁市の重要文化財 |
| 選定・表彰 |
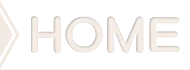
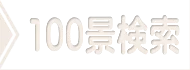

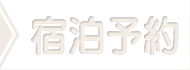



 Instagram
Instagram Threads
Threads X.com
X.com